関連アプリ: 対応のある2群の比較のSS計算 | 📊 対応のある群間の検定
対応のある2群の比較のための検出力の計算
厳密には「対応のある2群の個々の差の平均値と0との比較のための検出力の計算」です。
解説
対応のある2群間に実際に効果が存在する場合、その効果が統計的に検出される確率を指します。 検出力が高いほど、実際に存在する効果を見逃すリスクが低くなります。
具体例
糖尿病治療薬の効果を評価するため、患者の治療前後のHbA1c値を比較します。
- 対応のある値の群間差の平均値: 治療前後でのHbA1c値の平均的な変化が-0.5と仮定します。
- 対応のある値の群間差の標準偏差: 過去の研究やパイロット研究から、HbA1c値測定の標準偏差は1.0と推定されます。
- α エラー (有意水準): 一般的に5%(0.05)に設定します。
- サンプルサイズ: 研究に参加する被験者の数を設定します。例えば、30人と仮定します。
- 検定方法: 治療による悪化が考えられない場合は片側検定を、そうでない場合は両側検定を選択します。ここでは片側検定を使用します。
検出力の計算:
これらの情報を基に、検出力を計算します。HbA1c値の平均的な変化(0.5%)、標準偏差(1.0%)、αエラー(0.05)、サンプルサイズ(30人)を用いると、特定の効果サイズを検出する確率が得られます。
例えば、このシナリオでは、与えられたサンプルサイズと条件に基づいて、検出力は約 0.85 と計算されます。
このように、検出力を事前に計算することで、研究が実際に存在する効果を見逃さないように設計でき、より信頼性の高い結果を得ることが可能です。
サンプルサイズが大きいほど、また効果サイズが大きいほど、高い検出力が期待できます。 また、αエラーの設定と検定方法の選択も検出力に影響を与える重要な要素です。
アプリ
Reactive stat ロゴ について
ログインしていただければロゴは表示されなくなります
{{title}}
{{title}}
AI による R コードの解説
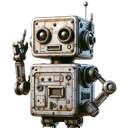
R の出力結果

R出力図形
AI による R 出力結果の解説
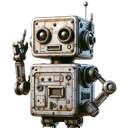
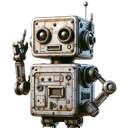
データ入力
結果
{{ reasonForNoResults }}
