2群の比率の比較(非劣性)のためのサンプルサイズの計算
等価性試験, 同等性試験, 優越性試験, 非劣性試験 の全てに対応したページがありますので、ぜひそちらをお使いください。
解説
非劣性試験とは
非劣性試験は、新しい治療法や介入が既存のものより劣っていないことを示すためのものです。 目的は「同等性」や「既存の治療よりも優れている」という主張ではなく、「十分に近い効果を持ち、既存の治療よりも劣っていない」という点を検証することです。
臨床的に意味のある差(非劣性マージン)について
「臨床的に意味のある差」は非劣性マージン(δ)と呼ばれ、新治療法が既存治療法より最大どの程度劣っていても臨床的に許容できるかを示す値です。
例: 既存治療の成功率が70%の場合、新治療が65%以上あれば臨床的に許容できるなら、マージンは-0.05(-5%)となります。 非劣性マージンは臨床的判断に基づいて事前に設定する必要があります。
サンプルサイズの計算
サンプルサイズの計算 は以下の要素を考慮して行われます
- 許容される差(臨床的に意味のある差)
- 希望する検出力(通常は80%など)
- 有意水準(たとえば5%)
- 検定方法(片側または両側)
検定方法によって、計算に使用される調整されたα値も異なります。 これにより、非劣性を確認するために必要な最小の参加者数が得られます。
検定方法
片側検定: 非劣性試験では通常、片側検定が用いられます。これは「新治療法が既存治療法より劣っていない」という一方向の仮説を検証するためです。
両側検定: 優劣どちらの可能性も考慮する場合に使用されます。
実用例
既存の降圧薬の有効率が60%、新薬の予想有効率が65%の場合で、新薬が既存薬より5%以上劣らなければ臨床的に許容できるとします。
この場合の設定値
- 対照群の比率: 0.60
- 被験群の比率: 0.65
- 臨床的に意味のある差: -0.05
重要な注意点
- 統計的有意性と臨床的意義は異なる概念です
- 結果の解釈には統計の専門知識が必要です
- 非劣性マージンの設定には十分な臨床的根拠が必要です
{{title}}
{{title}}
AI による R コードの解説
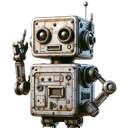
R の出力結果

R出力図形
AI による R 出力結果の解説
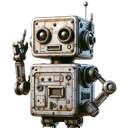
データ
結果
{{ reasonForNoResults }}
クラウド R 分析